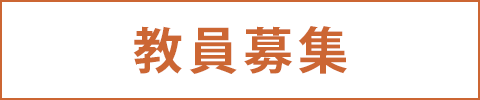学校法人日本コンピュータ学園 東日本航空専門学校
航空整備士、グランドハンドリング、グランドスタッフ、エアカーゴ、マーシャラーをめざすなら東日本航空専門学校
学科紹介

職業実践専門課程
整備士養成コース[3年制・男女20名]
整備技術コース[2年制・男女10名](ドローン操縦士資格取得)
航空機整備科
確かな資格取得で航空機整備のスペシャリストをめざそう!!
■国土交通大臣指定航空従事者養成施設
■二等航空運航整備士(基本技術Ⅱ)認定校

「二等航空運航整備士」として「基本技術Ⅱ」を取得し、航空整備士をめざします。
本校は、上位の航空整備士資格取得に必須となる二等航空運航整備士(基本技術Ⅱ)の認定校です。国家資格である航空整備士は、学科試験と実地試験(機体と基本技術)に合格する必要がありますが、「基本技術Ⅱ」を在学中に取得していれば、将来一等、二等航空整備士を取得する際の実地試験(基本技術)が大幅に免除となります。
コースのポイント


1)二等航空運航整備士100%合格継続中
3年制のため段階的に知識と技術を身につけるカリキュラムで、普通科出身の学生も合格を手にして卒業しています。
2)豊富な実習教材を使った専門教育
実機やカットモデル、模型などを「見て」「触れる」ことで基礎から理解を深め、未来の航空整備士を育てます。
めざす職業
確かな資格取得で航空機整備のスペシャリストをめざそう!!
航空整備士【ドック整備】

航空整備士【ライン整備】

小型機の整備

整備士養成コースの主な就職先
- ANAベースメンテナンステクニクス
- ANAラインメンテナンステクニクス
- JALエンジニアリング
- JAL CAF FLIGHT TRAINING
- AIRDO
- ジャムコ
- 中日本航空
- 東邦航空
- IBEXエアラインズ
- スカイマーク
- 航空自衛隊 ほか
学びのステップ
1年次
航空機の基礎からしっかり学ぶ
前期は整備技術コースと共に航空機についての基礎的な知識や技術、法規、機体、ピストン発動機などを学びます。就職試験対策としてSPIなどの基礎学力を習得し、整備マニュアルは国際語で表記されているので英語も学びます。後期から国家資格取得へ向けた授業内容を行います。


2年次
国家試験に向けてより高度な技術を習得
2年次では、より高度な知識・技術の習得に努め、学科試験合格を目標に学習します。機体実習・装備品実習など実技を通して、航空従事者として必要な安全意識に徹した知識、技術の習得をめざします。


3年次
即戦力として活躍するための総仕上げ
最終目標である二等航空運航整備士のライセンス取得(基本技術Ⅱ含む)のための技能審査合格へ向けて、これまで学んだ知識と技術をより確実なものとするための実践的な授業を行います。



基本技術Ⅱを修得するため学科・実技共に多くの授業時間数を確保しています。3年次9月に校内で行う技能審査(実技試験)では、口述試験と基本技術5科目の実技試験(締結作業、ケーブル作業、板金作業、機械計測、電気計測)があります。整備作業の基礎となる重要な教科です。
めざす資格・スキル
- 二等航空運航整備士(基本技術Ⅱ/飛行機)
- 航空無線通信士
- 危険物取扱者(乙種第1~6類)
- 特殊無線技士(航空)
- 実用英語技能検定
- TOEIC
基本技術Ⅱについて
| 基本技術Ⅱ | 運航整備士の上位資格である「航空整備士」を取得するのに必要な技術。本校では「基本技術Ⅱ」を取得するため、入社後、航空整備士の受験の際に試験科目が免除される。 |
|---|---|
| 基本技術Ⅰ | 運航整備士に必要な技術。この技術を取得できれば「二等航空運航整備士」になれる。 |

メッセージ
先輩からのメッセージ
M.S.さん
栃木県 東宇都宮工業高校出身
さまざまな機体の構造を学び、実際に整備や点検作業を行うのがとても楽しい!
オープンキャンパスに参加し、雰囲気が良く楽しく学べそうだと感じて進学を決めました。先生方は航空業界に従事された方が多く経験豊富なため、質問すれば何でも詳しく丁寧に教えてくれます。実習で行う機体の整備・点検作業では、機体の種類によって構造や搭載機器が異なるため、理解できたときに達成感があります。在学中に必要な資格を取得し、就職後も勉強を続けて航空機についての理解を深めていきたいと考えています。

先生からのメッセージ
航空機整備科
伊藤 秀吉先生
自分の夢を探しに来ませんか?
「航空業界って、どんなとこ?」「難しいんだろうなぁ。でも、ちょっと気になる。」「どうすれば飛行機の整備士になれるのだろう。」「飛行機も造ってみたいけど...」そんな気持ちが少しでもあれば、それを現実にしてみませんか。実習、学校生活を通して、それが決して不可能なことではないことがわかるはずです。今は飛行機に興味がなくても、整備士にむいている自分に気付くかもしれません。なぜなら、私がそうだったからです。まずは、学校で機体に触れて、体験してみてはいかがでしょう。。

卒業生からのメッセージ
株式会社 JALエンジニアリング
羽田航空機整備センター 機体点検整備部
航空整備士
佐藤 友美さん
福島県 平工業高校出身〈2012年度 航空機整備科卒業〉
新しいことや難しいことに挑戦して得られた経験は一生の財産になります
現在、大型機の重整備を担当しています。車では車検に該当する仕事で、主に計器等の電子、電気機器等の整備をしています。学生の時には、仕事に関する基本的な知識・技量をしっかり教えていただきました。一等航空整備士の資格取得では、その時のノートや実習の経験が役立ち、大変感謝しています。令和4年3月に一等航空整備士になり、その後航空機が安全運航できるか判断できるライン確認主任者の資格も習得しました。多くのお客様の命を預かる責任とその使命を負い、更なる知識・技量を習得して、安全運航を担う航空機整備の仕事に励みたいと思っています。